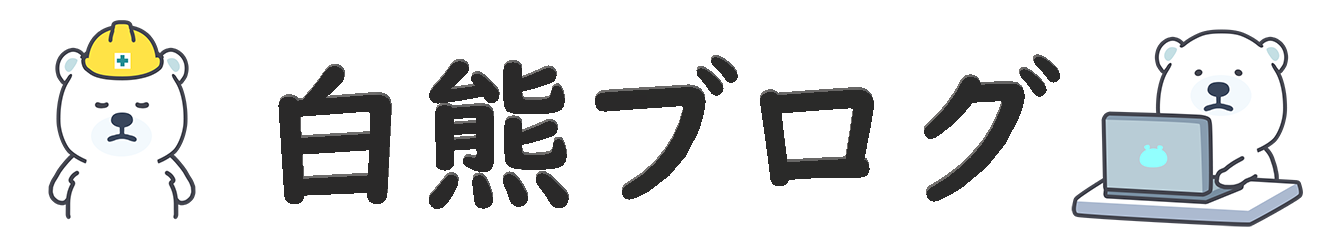・今からでも取り組んでほしいことの具体例
- わからないことがあったらすぐ聞く!
- メモを取ること!
- 資材や資材が何に使われるか知ること!
- ものの大きさ・重さを知ること!
- 工事がどこまで進んでいるか、確認すること!
1つずつ解説していきます。
先ほども言いましたが、現場は日々新しいことが増えていきます。
わからないことはすぐ聞かないと、
作業が進んでしまって聞く機会を失ってしまう可能性があります。
なので、なるべく早く聞くことが大切です。
でも先輩が忙しそうであったら、メモに書いておいて現場が閉所してから
聞くのがいいと思います。
(すぐ聞くことも大切ですが先輩への気遣いも忘れないようにしてください)
社会人になった方であれば、まずメモを取ることが仕事を覚える近道ではないでしょうか?
しかし私の中でメモを取ることは他の意味も考えています。
それは「先輩への敬意とアピール」です。
これはどういう意味かというと、「先輩の話をしっかりと聞いてますよ」と行動で敬意を
表し、先輩から見ると「あ、しっかり覚えようとしているな」と思われるアピールになります。
「メモを取らなくても覚えられるよー」という方もいると思いますが、
一種のパフォーマンスとして考えるのはいかがでしょうか?
先輩の教えようとするモチベーションにもなってきます。
工事の中であらゆる職種の作業があり、使う材料・資材は異なってきます。
職種ごとに使用材料を確認するには施工計画書の中の使用材料を見るのが一番早いですし、
その施工計画書と同じ材料が使用されているか現場で確認しないといけません。
これは材料検収といって現場に入ってきた材料を確認し写真に収める行為です。
材料検収を行わないと、設計やお客さん(施主さん)が本当にその資材でやったのか確認できなく
なってしまいます。(これをやると後々大変です)
施工計画書に作業手順も書いてあり、どこで材料を使用するかを丁寧な施工計画書には
記していますので、作業の流れと材料を確認するには施工計画書を見るのが一番
手っ取り早いと思います。
現場にある材料や資材等は、もちろん注文してサイズを決めるものもありますが、
真物と呼ばれる定尺のものもあります。
例えば、ベニヤの真物といえば909mm×1818mmのものを指します。
必要になれば材料屋さんに「ベニヤの真物を一枚ください」といえば909mm×1818mmの
ベニヤに現場に届きます。定尺のものに限らず、ものの大きさを把握しておくことで
材料を頼む際に調整ができるようになります。
それと材料や資材の重さをことで作業方法や危険性を知ることもできます。
例えばクレーンを使用して揚重作業を行う際も資材の重さをわかっていないと、
揚重する資材が定格荷重を超えないかはわからないですよね。
また内装作業などで職人さんが石膏ボードを壁に立てかけて作業してますが、
もし倒れてきた場合支えられると思いますか?
厚さにもよりますが、1枚11キロ~15キロくらいになります。もし10枚の束が倒れてきたら
支えられる気がしないですよね。ぺしゃんこにされます。
資材の大きさや重さを把握しておくことで、作業の計画をスムーズに立てることが
出来ますし、現場での危険性を知ることが出来ますので、気になる資材の大きさや重さを
知ることは大事だと思います。
工事は工程表を基に施工を進めています。
現場にいる職人さんやこれから乗り込んで作業を行う業者さんは工程表通りに作業を進めようと
努力しています。
なので、若手の皆さんは工程表を現場に持って行って今日はここまで終わったと確認することで
今後どんな作業行われるのか把握することが出来ます。
新しい工種が入ってくると周知会の準備であったり、写真管理は何をしたらいいのか?などと
予習もできますし、心の準備ができるようになります。
工程管理と品質管理は現場監督の仕事で重要になりますので、
現場で工程表をみて確認しているだけで「こ、こいつ 、次のことも考えてやがる」となります。
工程表見てもぱっぱらぱーなら(私もそうでしたが)工程表の内容を先輩に聞くといいですね。
その作業の施工計画書はこれだよと教えてくれることもありますので試してください。
おわりに
現場監督として働いてきたこれまでで良い先輩に教えられた方や、
全然教えてもらえなかったという方もいると思います。
偏見かもしれませんが現場で働く人は変わった人が多いです。
ただ一見変な人でも話してみたらフランクに話してくれる方もいますので、話しかけるという自発的行為を
行ってみてはいかがでしょうか?わからないことを自分の中だけで解決しようとしてもしきれないですし、
わからないことは今のうちしか聞けなくなっていきます。最初の現場が終わって、次の現場に行ったときに
「前の現場でやってるからできるよね?」といわれることもあります。
その時にちゃんとできるかは、今のうちから取り組めることをしっかり行っていった結果になります。
私自身、先輩にあまり教われず「標準仕様書」と「写真の撮り方」の本を渡されてほっとかれたので
本を見ながら写真を撮っていました。
先輩と歳が離れすぎていたのと現場が忙しかったので先輩は図面に集中していたので現場に
あまり出てきてくれませんでした。
その中でどうやったら仕事が覚えられるかと自分なりに考えて職人さんに聞いたり、事務所にいる
先輩に聞いて解決したりしていたので、自分自身がばたばたしていたかもしれません。
施工計画書の存在も入ってすぐではなく半年くらいたってから教えられたくらいですし、、、
みなさんには同じ経験をしてほしくないのと、今後の建設業界はITを多く取り入れていく時代に
入っています。なので基本的なことをできないと最新技術を扱うことは中々難しいですよね?
人手不足といわれている建設業界のなかでうまくやっていくことが出来るのかはみなさん次第ですが、
今回話させてもらったことを工事現場でできるようになれば基礎的なことは習得できますし、
今後みなさんに後輩ができたときに、まずこれをやっておけば大丈夫と教えることもできます。
もちろんほかの業務もありますが、その業務をやるだけでは機械的になってしまいますので、
能動的に動くことを意識して仕事をすることをおススメします。
自分のステップアップにつながります。
長々と書きましたが、工事現場で働くことはきついことが多いです。
現場で働く人たちの気持ちは重々わかります。ただその中でどう自分なりに動くかというのを
少しでも手助けできればと思いました。
参考になれば幸いです。
記事を読んでいただきありがとうございました。