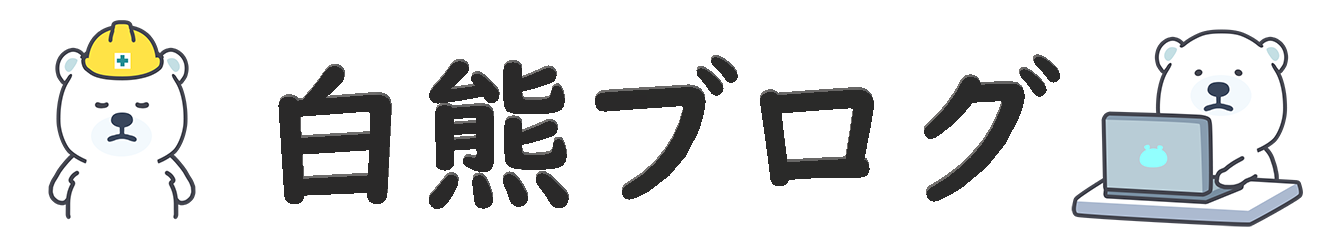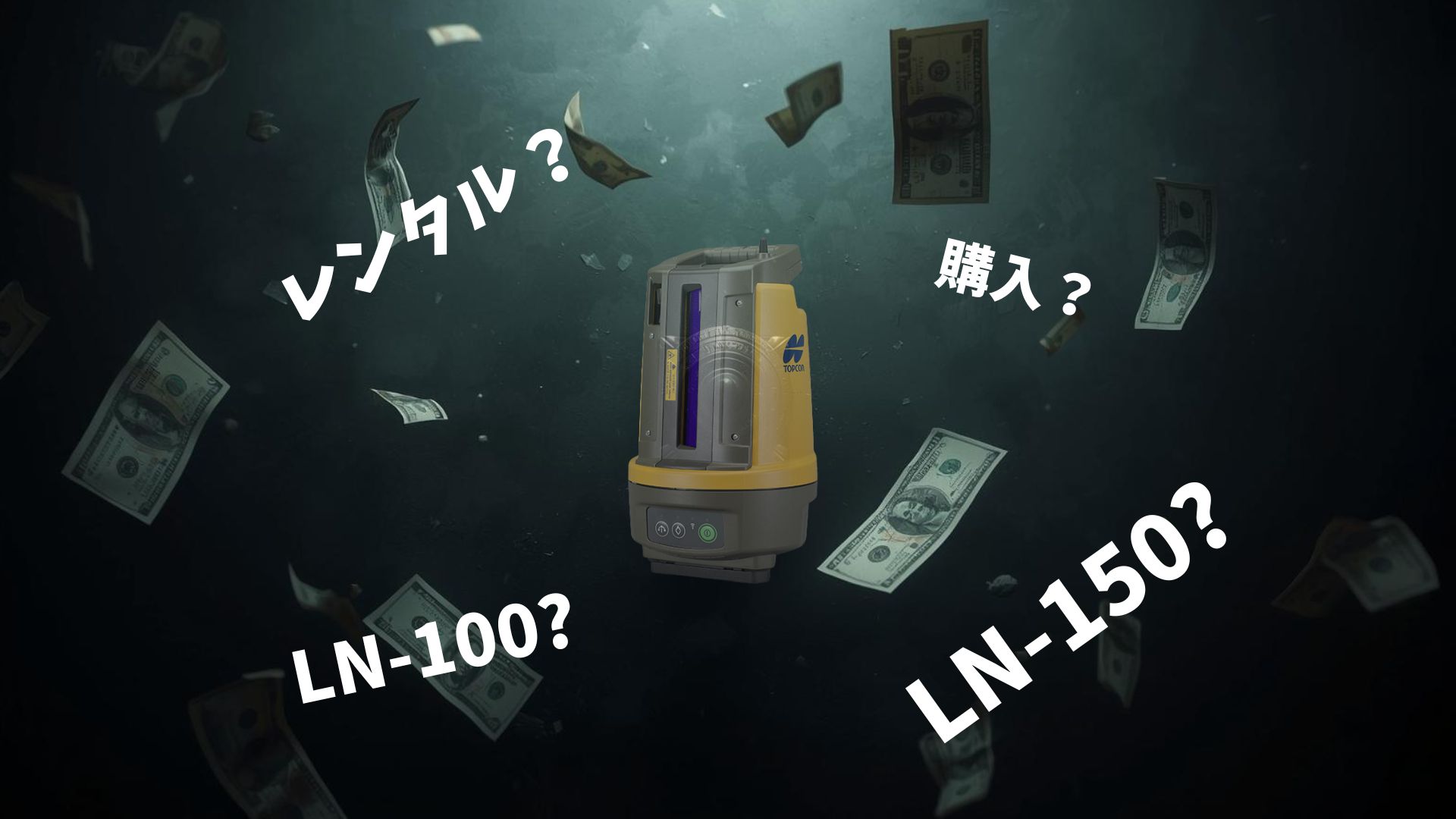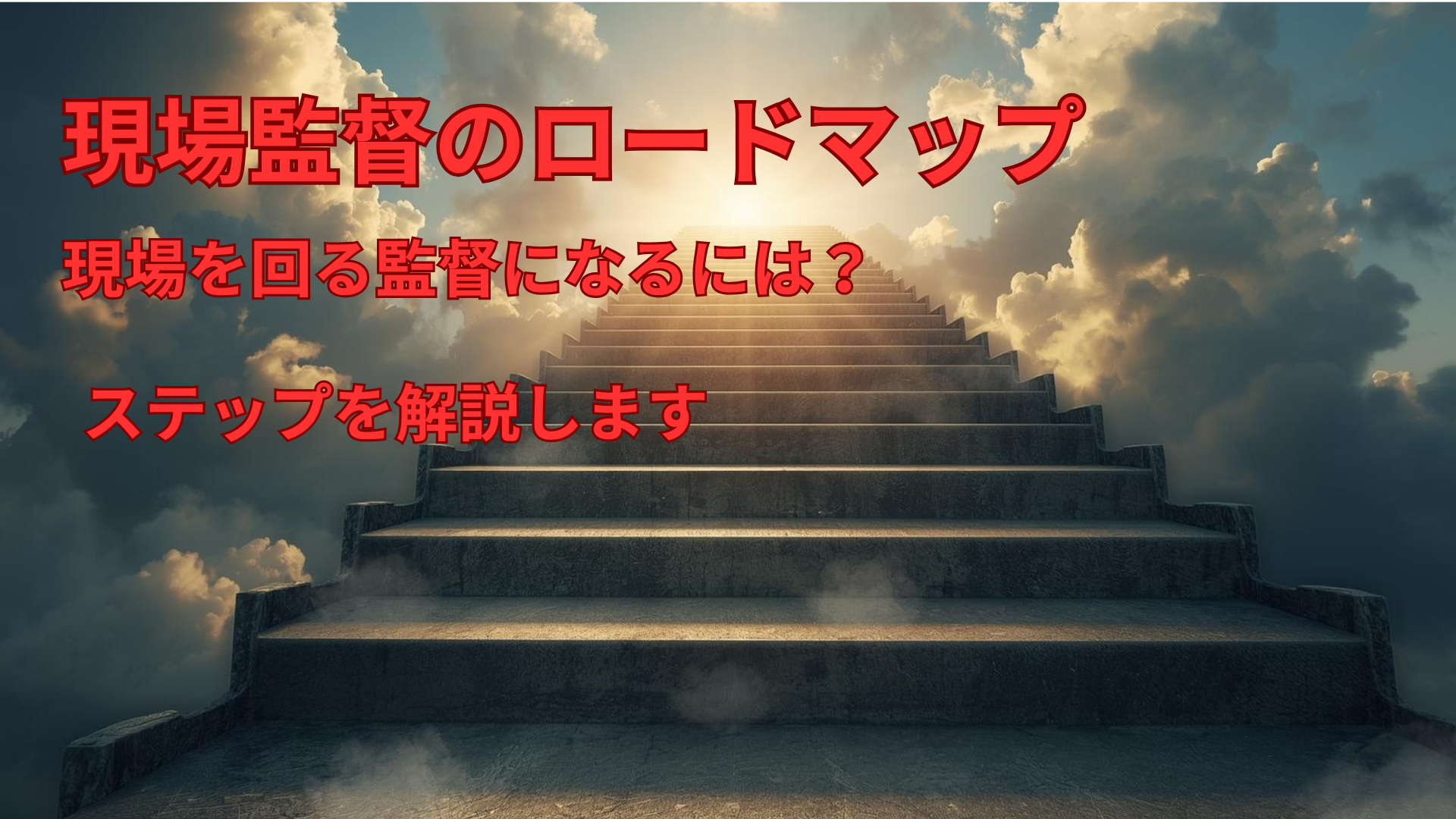
お疲れ様です!白熊です。
今回のブログは現役の現場監督である白熊が、
現場監督として、まずここを伸ばせば良い監督になるということを記事として書かせてもらいました。
あくまで私の考えなので参考程度にしていただければと思います。
建設現場の中心にいる現場監督は、「段取り力」・「図面を読む力」・「計画を工程に落とし込む能力」
の三つが揃ったときに初めて「回る現場」を作れるようになると考えております。
ここでは、現場監督として最短でスキルアップするためのロードマップを、
実務で使える具体的な行動と「私自身の実体験」を織り交ぜて解説していきます。
想定期間は1年〜3年で、毎月・四半期ごとの習慣とチェック項目を明確にしていきましょう。
目次
要点の先出
- 核となる3能力:段取り、図面力、計画力
- 最短の考え方(効率化):現場で繰り返し改善できる小さなPDCAを高速に回すこと。
- 成果指標:工程遅延件数、資材ロス率、変更対応時間、職長からの評価。
現場段取り力を最速で鍛える方法
段取りは「工程表を見ること」ではなく「現場が滞らない状態を設計すること」です。
下記を毎週・毎日ルーティーンに落とし込むことができるようにしましょう。
・毎朝の30秒チェックリストを作る。
主な項目は当日の作業、搬入予定、資材保管場所の確認、次工程が何かを確認する作業。
・週間工程表は逆算型で作ることを。
完成日から逆算して、前工程の余裕日数とリードタイムを確保する。足りない場合は調整。
・資材手配は発注→搬入→保管→作業の流れを一枚のフロー図にする。(打合せ時に確認)
業者滞納時の代替ルートと連絡先を常備する。
置き場所は「作業場所に最短で届くこと」を優先する。
動線とフォークリフト/人力の可視化図を現場に掲示する。
現場レイアウト図(フォークリフト動線・資材ゾーン・動線を色分け)
図面を読む力を速習で身につける
図面を読む力を身につけるには「線を読む」だけでなく「現場でどう作るかを想像する力」です。
以下を段階的に実行しましょう。
・図面の目的別分類を覚える。設計図は意図、施工図は実行、製作図は細部。
設計図だけでは現場を納めることはできないです。施工図と製作図を見ることで現場にどういったものが
取り付けられるかを確認することができます。
・製作図と現場の整合は寸法→取り合い→取付順序の順でチェックする。
特に取り合い(納まり)は手戻りの要因ことが多いです。
サッシなどの製作物は現場での加工ができないので、ます図面と現場が合っているかを確認し、
不整合があるのであれば製作物が来るまでに解消しておかなければなりません。
ある程度図面を見ているだけで「ここにはサッシが来るな」とか
「あれ?ここの躯体出ていて大丈夫か?」などの現場で気が付けることもあります。
・3Dの考え方を持つ。
平面で合っていても高さなどで上部にあるものと干渉が原因で施工不可になる場合があります。
平面図と断面図を見ながら、図面の該当部と比較する習慣をつけることが大事です。
BIM(3Dビューア)などに最低限触れることで立体的な考え方が習慣化します。
計画力 実務で成果を出す打合せ術と工程落とし込み
計画力は対人スキル+技術スキルが鍛えられます。工程へ確実に落とし込む方法を記載します。
施工業者とは施工前に打合せを行いますがそこでのポイントも紹介していきます。

・事前打合せのコツ
業者との事前打合せでは目的を明確にし、決めるべき事項を箇条書きにして書き出しておきましょう。
議事録の中では合意済みと未解決リストを分けておき、後日メール等でやりとりを行いましょう。
結論は必ず「誰が」「いつまでに」「何を」するかを打合せの際に確認しておきましょう。
・施工について調整のコツ
「施工時期」「工程」「必要な環境」を確認しましょう。
この時期に入ってくださいと言っても、現場で作業出来る状態でなければ意味を成さないですよね。
作業に必要な環境を整えるために事前の打合せで、必要な資材置き場や足場の要否などの作業環境の
希望を聞いておきましょう。
利害が対立する場合は「最小公倍数」案を用意する。妥協点を予め想定して提示すると合意が早い。
「うちは今までこうしてきた」では話がまとまらないので、「ここはこうして」などギブアンドテイクの
提案ができるといいと思います。
・工程への落とし込み
打合せで決まった内容に基づいて、工程に落とし込みましょう。
隣接作業や上下作業にならないように他の工種との取り合いに気をつけながら配置を考えていきます。
会議で決まった内容を工程表へ反映し、関係者へ更新版を流す。
小さな変更でも必ず関係者へ通知し、記録を残す。
1年目〜3年目の月別・段階別ロードマップ
1年目(基礎構築)
- 月次:現場に慣れること。朝礼・KYを主導する。図面・施工計画書を見て工事写真を撮る。
- 四半期:工程表を読むことに努める。資材手配の流れを理解する。
2年目(実務化)
- 月次:上司と共に工程表を作成する。週間工程でも。現場レイアウトを最適化を考える。
- 四半期:製作図と現場の突合せを主導。小規模の打合せを取りまとめる。(打合せに参加する)
3年目(統括力)
- 月次:複数工程の同時進行管理ができる。協力会社と工程調整を行う。
- 四半期:工程遅延の根本原因分析と再発防止策を立案・実行する。(上司と共に)
最後に 実行優先順位と習慣
毎日の習慣化が最短距離になリます。まずは下記の三つを習慣化すること。
- 毎朝の30秒チェックリストを実行する。
- 打合せ結果を工程へ即座に反映し、関係者に確認を行う。
- 毎週1回、拾い出しと現場突合せを行う。
これを続ければ、3か月で段取りの精度が上がり、1年でチームからの信頼が得られる。
実務に直結する小さな改善を高速で繰り返し、図面と現場、計画と実行のギャップを埋め続けることが現
場監督としての最短の成長路です。
実体験をもとに
1年目の時は中々自分の仕事の流れというものがわからず、言われたことを優先でやっていると
自分の仕事が疎かになり、仕事のやる気が薄れていきます。責任感を持つことが大事ですが、
「いや、上司に呼ばれたから」と仕事を中途半端にしまいがちです。
そうならないために自分の仕事の予定や今日はここまで終わらせておけばいいと区切りを設けることで
他の時間は上司の対応や急な仕事での対応用に余裕をとっておけます。
思いつきで話してくる人はいますので。
現場監督は大変な仕事で、「現場は生き物だ」と言われて、施工の進捗具合は常に見ておかないと
気がついたら工程から外れているなんてこともよくあります。
こちらからしたら「打合せしたんだから工程通り終わらせろよ」と思うところもありますが、
出来ないことは出来ないと割り切ることが大事で、解決方法や次工程への影響を考えて進めるように
しましょう。内心はムカついていますが。
また、茶々を入れてくる上司などもいるでしょう。施工が始まってから文句をつけるやつがいますが、
そういったやつは計画時に一緒に打ち合わせをさせるなど、「いや、聞いてたでしょ?」と
言えるようにしておくと何も言ってきません。責任も取れないのであれば偉そうにするなと。
責任を取ることができない人と仕事すると無駄ですし疲れるだけなので。